プロセスエコノミー読んでみた
WHYからはじめるべき現代では有効っぽい手法です!!
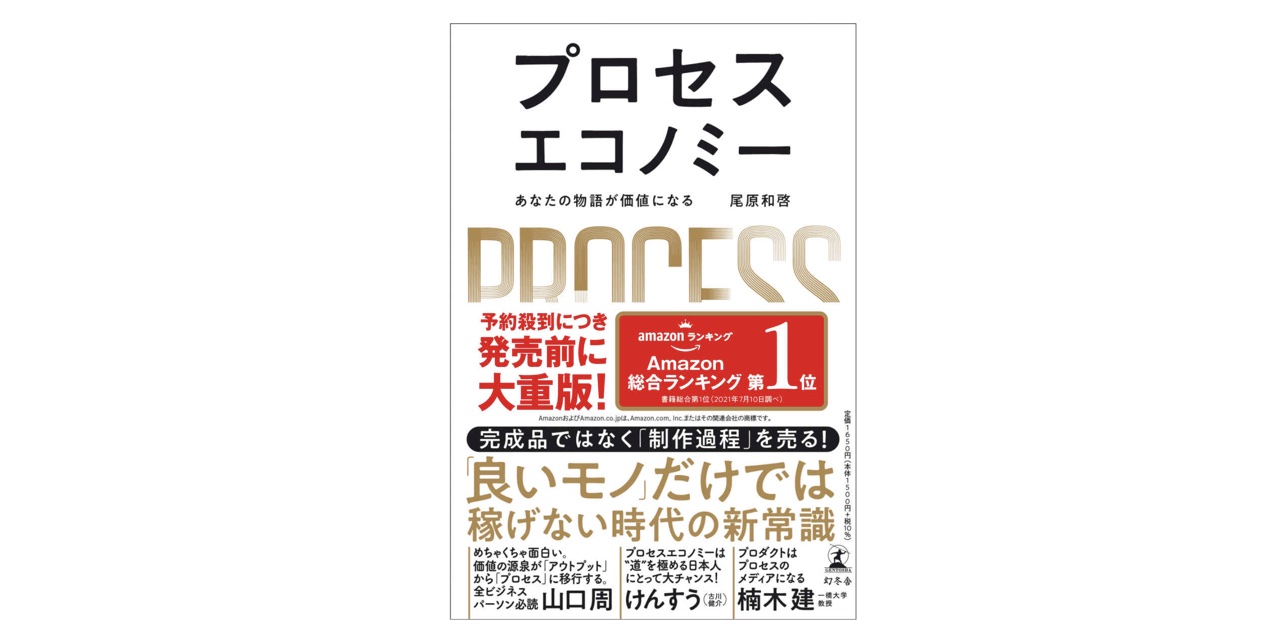
結論から言うと、
「プロセスエコノミーとは
プロセスに課金するための手法で、
WHYから始める現代で
有効っぽい手法である」
というのが魚田の感想です。
その理由とか、
「有効っぽい」と
自信なさげな理由に
興味ある人は読み進めください↓
・・・
改めまして、魚田です、
プロセスエコノミーという本を
改めて読んでみました。
(2年前に買ってましたが未読破でした)
大前提として:現代はクオリティでは差別化できない時代
①ノウハウは本やYoutubeで溢れている
②口コミで淘汰されるスピードがアップ
そのため、すべての水準が
上がりきった結果、
- 品質もいいし、
- 値段も手頃だし、
- 流通もしっかりしている
モノにあふれ、
差が小さくなっているためです。
よほどこだわりがある消費者以外は
「ユニクロでいいや」現象。
では、ぼくたち起業家は
どこで差をつけるか?
答えは「ストーリーやプロセス」
- NiziU
- 各種メイキング
- ドキュメンタリー
などがイメージしやすいと思います。
これらはプロセスをパッケージして
売っています。
プロセスエコノミーは
もうちょっと大胆で、
「プロセスに付加価値があるなら
プロセスに課金しちゃえば
いいんじゃないの?」
という試みです。
けっこう身近に
プロセスエコノミー例があります(後述)
「役に立つ」より「意味がある」
コンビニは1種類の
ハサミしか売ってません。
しかし、タバコは200種類売ってます。
(ぼくもバイトしたとき
銘柄覚えるのに苦労しました)
効率至上主義のコンビニで
なぜ200種類も売っているのか?
儲かるからです。
もっと言うと、
セブンスターを愛飲している人にとって
セブンスターという銘柄は代替不可能。
だからメジャーな銘柄は
揃えておく必要があるのです。
(ぼくはタバコ吸わないので、
アタマで理解できても
共感できないです。
喫煙者の方よかったら
コレ本当か教えてください)
「グローバル・ハイクオリティ」か「ローカルコミュニティ」か
これからの戦略は
ざっくり言うと2種類しかないです。
「役に立つ商品」で世界一になるか
「意味のある商品」でローカルを捕るか。
(で、ぼくらひとり起業家は
基本的に後者でしか勝負できません)
(例外はスタートアップ。
まだ世の中にないものなら
投資家を巻き込みながら
一番乗り=世界一を狙えるかも?)
「意味」を欲しがっている消費者は、
「意味」を共有できる仲間や
コミュニティをセットで欲しくなります。
友人が使っていて
オススメされたから
使ってみた、
はよくあるケースでしょう。
ぼくもアイマスに沼った後、
その「意味」を共有できる
「仲間」を切望しました。
家族、ご近所、会社、という
既存のコミュニティが
希薄になっている現代、
所属欲求は強くなっています。
また、テクノロジーが
プロセスエコノミーを
加速させるかも?という話も。
太陽光発電の効率が良くなり
2050年には電気料金が
10分の1になるのでは?
なんて予測まで書いてあります。
電気料金が10分の1になると
LEDで野菜工場が作れ、
食品がもっと安くなります。
ますます飢える心配のない世界になり、
人々は相対的に
「人間関係」や「没頭」の
要求がますます強くなる可能性があります。
つまり、ますます
WHYとプロセスエコノミーが
大事になるかも?
プロセスエコノミーを語る上で
「物語」という部分も欠かせないのですが
本記事では割愛。
プロセスエコノミーの実例:
●BTSをはじめとするK-POP
強烈なファンは
クラウドファンディングによって
お金を出し合い、日本でいう
渋谷109みたいな場所に広告を出すそうです。
肖像権をガチガチにしてないので
応援目的の広告は大歓迎だそうで。
YoutubeでBTSの曲を流したり
ファンが踊ってみたを流したり
コメントつけたりするのも自由。
日本のニコニコ動画を彷彿する、
オタク心をくすぐる試みだなぁ、
と思います。
(日本のアイマスやラブライブでも
ファンがお金を出し合って
フラワースタンドを
送ったりする文化があります)
●ジャニーズ
日本のジャニーズも
プロセスエコノミー的な
要素があります。
デビュー前のがんばるメンバーの
プロセスを無名の時代から応援できる
これも実にオタク心を
くすぐります。
こういうのに
オタクは弱いのを秋元氏は
良く理解していますね。
最終成果物である音楽が
ほぼ無料で聞ける現代。
音楽マーケットは縮小したかというと
ライブ、コンサート市場の売上は
この10年で倍になっています。
メルカリで野菜を売る農家
メルカリで野菜を売る農家には
2つのメリットがあります。
農協を通さなくていいので
中抜きされない、つまり安くできます。
そしてストーリーも
売ることができることです。
野菜とともに
「嵐で大変でしたが、
こんなトマトが出来上がりました」
「今年の青森ニンニクは
出来がすごいですよ」
などと、生産者が直接書く。
写真と共に野菜を送る。
消費者は農家のストーリーも
一緒に買うことができ、
単なるリピート率向上に留まらない、
「共犯関係」とも言うべき
一体感を作れます。
(本書で紹介されている実例は
まだまだたくさんあるので
興味ある人は手にとって見てください)
プロセスエコノミーの実践方法
プロセスエコノミーでは、
WHYを語るのが極めて大事です。
WHYを説明するには
サイモン・シネックの
「WHYから始めよ」
という動画が分かりやすいです。
AppleのWHYはこうです、
「私達は情熱を燃やす人を応援している」
「なぜなら情熱を燃やす人は、
世界をより良い方向に導くから」
そのためのアイテムがMacだったり
iPhoneだったりしているだけ。
そんなスタンスをとっています。
WHYが無い場合「キックスターターの悲劇」
日本のCAMPFIREみたいに
アメリカにもKickstarterという
クラファンプラットフォームがあります。
で、ここで性能ばっかり
語ったいいアイテムが
資金調達に成功しても
2週間後には
性能は8割だけど価格は半分の
類似品が中国から売られる、
なんてことがよく発生するそうです(泣)
1個買って、
中身バラせば
だいたい分かりますからね。
要は、プロセスに「WHY」が
こもっていないとカンタンに
真似されてしまいます。
逆に言えば、
WHYがこもっている場合、
「創始者の謎の情熱」とか
「変態性とか偏愛」とか
そういう部分から生まれる
プロセス・ストーリーは
カンタンには
コピーできないのです。
最後にこの本は
プロセスエコノミーが害になる
パターンも紹介して
締めくくられています。
魚田の感想としては、
プロセスエコノミー、
とくに中核にくる
「WHY」の大切さは
理解できたのですが、
それを上手く伝える手法が
今ひとつ抽象論で
ぼくには腑に落ちなかったです。
プロセスエコノミーの
要素を入れれば成功する、
って単純な図式では
ないですからね。
いろんな人が絶賛研究中の、
新しい分野だからこそなんでしょう。
興味ある方は
ぜひ目を通してみてください。
魚田じゅん
このブログは、
あなたに役に立つ情報を
書きたいと思っています。
↑で匿名で質問することができるので
良かったらお気軽に質問ください!
